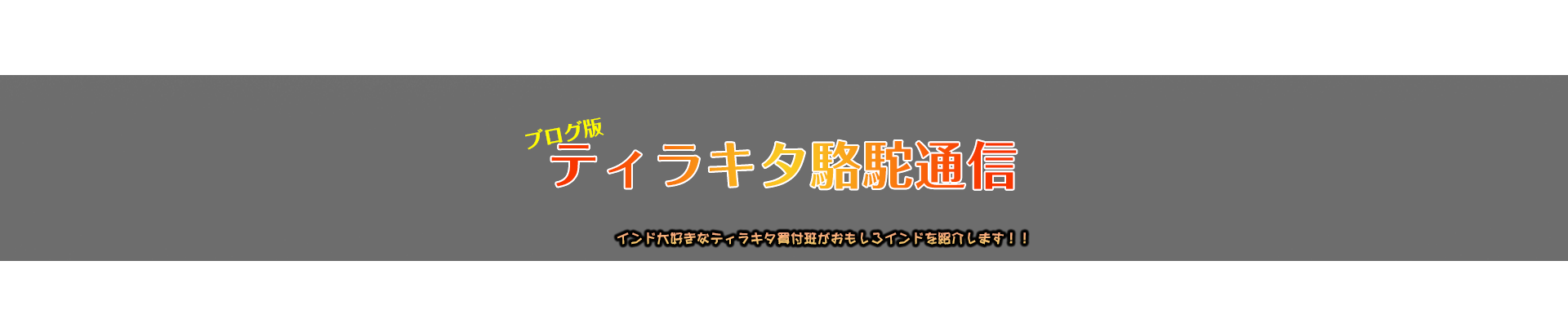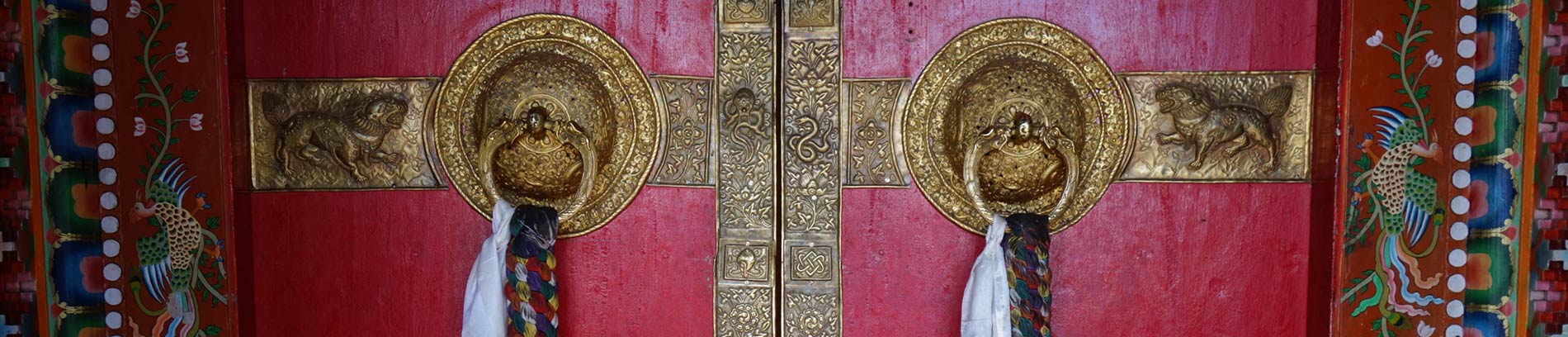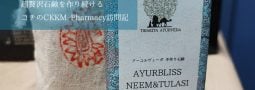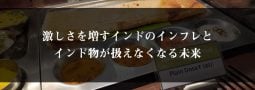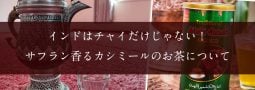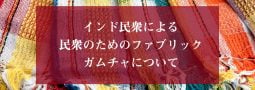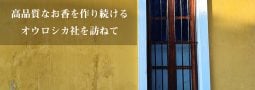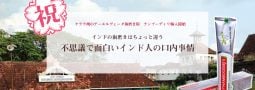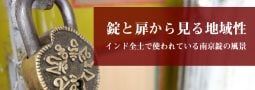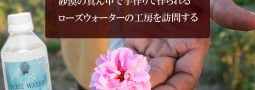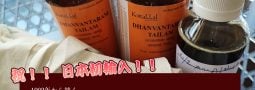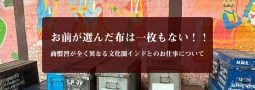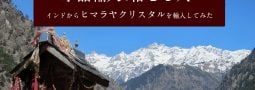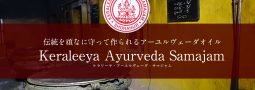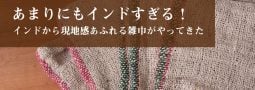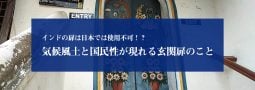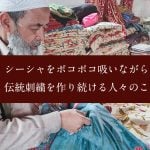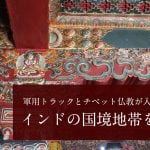インドのスイーツが極端に甘いのはなぜなのか?

■死ぬほど甘いインドスイーツ
インドスイーツを一度でも口にしたことがある人はご存知かと思いますが、インドスイーツは、頭の芯がジンジンするほど極端に甘いのが特徴です。
こちらの茶色い団子状のものはグラブジャムンというスイーツですが、グラブジャムンはコアと呼ばれる乳製品に小麦粉や砂糖水を混ぜ、そして油で揚げ、また最後に砂糖水につけて作られます。
乳製品に小麦粉と砂糖を混ぜたものを揚げ、ダメ押しにまた砂糖汁に浸すと言う、乳脂肪+砂糖+炭水化物+砂糖という極悪な組み合わせのインドスイーツ!!!
まさに太れ!! そして糖尿病になれ!! と言ってるようなスイーツです。

こちらの白いボール状のものはラスグッラと呼ばれるもので、こちらもまた激甘スイーツです。ラスグッラはパニールと呼ばれるインドのチーズをベースにし、そこにベーキングパウダーと小麦粉を入れてこね、ボール状にします。
出来あがったボールをローズウオーターの香りをつけた砂糖水につけるという、こちらもまた乳脂肪+砂糖+炭水化物と言う、極悪な組み合わせのお菓子です。

こちらのぐるぐるととぐろ状になっているスイーツはジャレビーです。
ジャレビーは小麦粉と水を混ぜてこねて作った、持ち上げれば垂れてくるくらいに緩い生地を、ぐるぐると円形状にして油で揚げ、揚げたものを即座に砂糖水につけるという炭水化物+油+砂糖というこれもまた、殺人的な一品です。
ちなみにジャレビーの横の薄茶色のドリンクは、スイートミルク。牛乳にカルダモン味をつけ、砂糖を大量に投入したもの。
スイートミルクとジャレビーを一緒に食べたら、血糖値があっという間に上昇して、軽くハイになれると言う、フードドラッグ的な側面を持つ一品です。
■ スイーツ屋さんの店内を覗いてみると
インドでスイーツ屋さんを訪問してみました。デリー市内にあるアグラワル・スイーツショップです。デリーの名所、巨大ハヌマン様の近くにありました。

インドのスイーツ屋さんでは日本のスイーツにあるようなケーキなどはほぼなく、インド風のスイーツである、ラスグッラ、ラスマライ、カトリ、そしてクルフィなどが売られています。

よく見てみるとガラスケースの中に入ってはいますがガラスケースに冷蔵機能は付いていません。スイーツは冷やさなければいけないものの気がしますが…インドのスイーツは冷やさなくてもいいのでしょうか。

あ、もちろんアイスクリーム的なお菓子もありますよ。クルフィと言うアイスキャンディーで、カルダモンの味がします。でも、こういった冷やさなければいけないスイーツはとっても少数ですね。

■ 甘いのには理由がある
インドのスイーツがなぜこんなにも甘いのか。
そこにはいくつかの理由が考えられます。
一つ目の理由は、そもそもインド人達があまりお酒を飲まない事です。お酒を飲まないと体が糖分を欲しがるので、甘党になりやすい言うのは日本でもよく知られているところ。

インドの人たちがお酒を飲まないのは、宗教的な理由ですが、国民の多くがあまりお酒を飲まないので、自然と国全体が甘党になっていくと言うシナリオが考えられます。このような状況はイスラム国でもよく見られますね。ティラキタ買い付け班の今までの旅行経験からも、スイーツが美味しい国は、お酒を飲まない国が多かったなって思いますし。
とは言うものの、甘いのだって限度を超えたら毒になります。
インドは世界有数の糖尿病大国として知られていますが、その理由の一つは、この甘いスイーツにあると思うんですよね!!
こんな甘いスイーツを食べて、体を壊して糖尿病になっちゃうインド人たち。
「そんなに甘くしなきゃいいじゃない!!」と私達日本人には不思議で仕方ありませんが、インドの気候や生活環境に根ざしたもう一つの理由がありました。
その極端に甘い理由は保存のためです。
甘い料理は腐りにくいのです。
感覚的には、甘いとすぐ腐りそうな気がしますが、実際にはその逆で、甘くすると腐らないんです。
砂糖が50%以上含まれている食品では、一般的な細菌はほとんど繁殖することができません。
甘くすればするほど食品が長持ちして腐らない。
甘いものを十分に甘くしておけば、食品が腐らないということを、インド人達は昔からの知恵として知っていたのでしょう。
インドの夏は過酷な暑さで気温が40度や45度になったりします。
45度の酷暑の中、冷蔵庫なしで食品を保存しなければいけないのです。
過激なまでに甘いスイーツの理由は、保存食でもあり、また、お酒を飲まないから国民全体が甘党になると言う両方の要因から来ているのでした。
物事には何でも理由があるものなんですねぇ