アタ籠の製作工程を見てきました!
 つい先日、素敵なハンディクラフトを求めてバリ島に行ってきました。バリ島と言ったら、サーフィンや音楽、観光で有名ですが、ハンディクラフトにも素晴らしい物が多いのです。
その中の一つにアタと言うつる草を使ったハンドメイドの籠があります。この籠、おみやげ品としてもよく見かけますし、日本にも古くから輸入されてきていますので、知っている人も多いのではないかと思います。でも、おみやげ品として売られているものを購入したからといって、お値段的にも品質的にもお客様に喜んでもらえるわけがありません。何でも源流まで確認してみたいティラキタ買い付け班、なんと、アタ籠の村まで足を運んでしまいました!
このアタの籠、クオリティの高い良い物が簡単に手に入る訳でありません。バリ島東部の端っこにバリ・アガと呼ばれるバリ原住民の人たちの村があり、良い物はそこでしか作っていないのです。クオリティの低い「おみやげ品」は他の村でも作っているそうですが、クオリティの高い、日本人の評価に耐えるアタの籠はその村だけ。
アタ籠の村は遠いので、前の日は早く休み、朝早く出発です!! 地図上では67Kmしかない所ですが、ホテルがあるクタから4時間位の道のりでした。バリは小さな島で、道路もあまりきちんとしていません。一応、ハイウェイと呼ばれる道はあるのですが、どう見ても日本の国道レベルで、ハイウェイと言う感じではありません。特に大きな街中は道が狭く、いつも渋滞ばかりしています。
「なんで道を広げないの?」と聞くと、「バリには色々な所にお寺があるでしょ? そのお寺を動かすのが大変なのよ」との答え。「別の所の土地を買って、そこに作るわけにはいかないの?」と聞いたら「お寺を動かすには、動かす前に何回もお祭りをして、動いた後もまたお祭りをして。お寺を動かすくらいだから盛大にお祭りをやるでしょ? みんな、そのためのお金がないのよ」といかにもバリらしい答えが帰ってきました。
経済効率を考えて、すぐに大きな道路を作ってしまう私達と、神様のことを考えてなかなかお寺を動かさず、いつも渋滞ばかりしているバリ。一見、私達のほうが豊かな感じがしますが、でも、本当は昔の街並みがいつまでも変わらないバリのほうが豊かなのかもしれません。
街中を走り、途中でライステラスに出ました。バリらしい、美しいライステラスです。バリでは年に4回もお米が取れるのだそう。ライステラスを抜けて海沿いの田舎道をどんどん走り、だいぶ疲れた頃、アタ籠の村に到着です!!
つい先日、素敵なハンディクラフトを求めてバリ島に行ってきました。バリ島と言ったら、サーフィンや音楽、観光で有名ですが、ハンディクラフトにも素晴らしい物が多いのです。
その中の一つにアタと言うつる草を使ったハンドメイドの籠があります。この籠、おみやげ品としてもよく見かけますし、日本にも古くから輸入されてきていますので、知っている人も多いのではないかと思います。でも、おみやげ品として売られているものを購入したからといって、お値段的にも品質的にもお客様に喜んでもらえるわけがありません。何でも源流まで確認してみたいティラキタ買い付け班、なんと、アタ籠の村まで足を運んでしまいました!
このアタの籠、クオリティの高い良い物が簡単に手に入る訳でありません。バリ島東部の端っこにバリ・アガと呼ばれるバリ原住民の人たちの村があり、良い物はそこでしか作っていないのです。クオリティの低い「おみやげ品」は他の村でも作っているそうですが、クオリティの高い、日本人の評価に耐えるアタの籠はその村だけ。
アタ籠の村は遠いので、前の日は早く休み、朝早く出発です!! 地図上では67Kmしかない所ですが、ホテルがあるクタから4時間位の道のりでした。バリは小さな島で、道路もあまりきちんとしていません。一応、ハイウェイと呼ばれる道はあるのですが、どう見ても日本の国道レベルで、ハイウェイと言う感じではありません。特に大きな街中は道が狭く、いつも渋滞ばかりしています。
「なんで道を広げないの?」と聞くと、「バリには色々な所にお寺があるでしょ? そのお寺を動かすのが大変なのよ」との答え。「別の所の土地を買って、そこに作るわけにはいかないの?」と聞いたら「お寺を動かすには、動かす前に何回もお祭りをして、動いた後もまたお祭りをして。お寺を動かすくらいだから盛大にお祭りをやるでしょ? みんな、そのためのお金がないのよ」といかにもバリらしい答えが帰ってきました。
経済効率を考えて、すぐに大きな道路を作ってしまう私達と、神様のことを考えてなかなかお寺を動かさず、いつも渋滞ばかりしているバリ。一見、私達のほうが豊かな感じがしますが、でも、本当は昔の街並みがいつまでも変わらないバリのほうが豊かなのかもしれません。
街中を走り、途中でライステラスに出ました。バリらしい、美しいライステラスです。バリでは年に4回もお米が取れるのだそう。ライステラスを抜けて海沿いの田舎道をどんどん走り、だいぶ疲れた頃、アタ籠の村に到着です!!
 アタの村は海岸から車で10分位入った山あいにありました。村は山の一番下にあり、周辺が山に囲まれています。村全体が石造りの壁で覆われていました。広い村を外敵から守るかのように高さ2m位の石壁が続いています。草木で葺かれた建物が並び、昔にトリップしたかのような懐かしい雰囲気です。カゴの中に鶏が飼われているのがまた懐かしい感じを増幅しています。車がない時代に村の基本設計がされたらしく、歩く方が便利です。大変田舎で、とても懐かしく、とても不思議な雰囲気の村でした。こんな所で世界的に有名なアタ籠が作られているなんて想像もできません。
アタの村は海岸から車で10分位入った山あいにありました。村は山の一番下にあり、周辺が山に囲まれています。村全体が石造りの壁で覆われていました。広い村を外敵から守るかのように高さ2m位の石壁が続いています。草木で葺かれた建物が並び、昔にトリップしたかのような懐かしい雰囲気です。カゴの中に鶏が飼われているのがまた懐かしい感じを増幅しています。車がない時代に村の基本設計がされたらしく、歩く方が便利です。大変田舎で、とても懐かしく、とても不思議な雰囲気の村でした。こんな所で世界的に有名なアタ籠が作られているなんて想像もできません。
 車を降りてみると、村の色々な所にアタ籠の半完成品が干されていました。でも、私達が見たことのある飴色のアタ籠ではなく、まだ緑色のフレッシュなアタ籠です。
車を降りてみると、村の色々な所にアタ籠の半完成品が干されていました。でも、私達が見たことのある飴色のアタ籠ではなく、まだ緑色のフレッシュなアタ籠です。
 村の中に入って、アタ籠を燻す工程を見せてもらいました。村人に案内されて村の外れに行き、一軒の家の門をくぐります。外側はブロックで作られ、全面に金属の黒い蓋が付いている大きな釜がありました。黒い金属の蓋は長く使われているらしく、テカテカと油で光っています。言うまでもなく、それが燻製器でした。日本でキャンプ用に売っている燻製器の100倍くらいの大きさです。
おばさんが中を開けてくれました。もうもうと立ち上がる煙がおさまると、ちょっと茶色くなったアタ籠が顔を見せました。さっき見た緑色のアタ籠をこの釜の中に入れ、3日間程燻すと、アタ独特の飴色になるのだそうです。綺麗な色になるだけでなく、虫よけにもなるのだとか。3日間の間、ずっと燻製釜の中に入れっぱなしではありません。たまに開けて、色の付き具合をみたり、ムラができないようにひっくり返したりします。燻すにもきっとテクニックがあり、難しい工程なのでしょう。
村の中に入って、アタ籠を燻す工程を見せてもらいました。村人に案内されて村の外れに行き、一軒の家の門をくぐります。外側はブロックで作られ、全面に金属の黒い蓋が付いている大きな釜がありました。黒い金属の蓋は長く使われているらしく、テカテカと油で光っています。言うまでもなく、それが燻製器でした。日本でキャンプ用に売っている燻製器の100倍くらいの大きさです。
おばさんが中を開けてくれました。もうもうと立ち上がる煙がおさまると、ちょっと茶色くなったアタ籠が顔を見せました。さっき見た緑色のアタ籠をこの釜の中に入れ、3日間程燻すと、アタ独特の飴色になるのだそうです。綺麗な色になるだけでなく、虫よけにもなるのだとか。3日間の間、ずっと燻製釜の中に入れっぱなしではありません。たまに開けて、色の付き具合をみたり、ムラができないようにひっくり返したりします。燻すにもきっとテクニックがあり、難しい工程なのでしょう。
 燃料として使われているのはココナッツの外側です。ただの木のかけらに見えますが、一旦火が付いて燻されると良い香りが出ます。実際、フレッシュな作りたてのアタ籠は燻製のやさしい香りがします。
燻し終わったら最終的な検品です。ちょっと出ちゃっている所などを爪切りでプチプチと切ります。まだ小学生くらいの若い子から、60歳以上のお婆ちゃんまで10人ぐらいが一箇所に集まって仲良く検品作業をしていました。
「そういえば、ここで編んでいる人はいないの?」と聞くと、「この村では燻して、最終加工をするだけなんだよ。編むのは長い時間がかかるから、山の中の自宅でやっているんだ」とのこと。山の中には1000人以上の人たちがアタを編んで暮らしているそうです。そして、出来上がり次第、このアタの村にやってきて、お金をもらって帰るのだとか。
燃料として使われているのはココナッツの外側です。ただの木のかけらに見えますが、一旦火が付いて燻されると良い香りが出ます。実際、フレッシュな作りたてのアタ籠は燻製のやさしい香りがします。
燻し終わったら最終的な検品です。ちょっと出ちゃっている所などを爪切りでプチプチと切ります。まだ小学生くらいの若い子から、60歳以上のお婆ちゃんまで10人ぐらいが一箇所に集まって仲良く検品作業をしていました。
「そういえば、ここで編んでいる人はいないの?」と聞くと、「この村では燻して、最終加工をするだけなんだよ。編むのは長い時間がかかるから、山の中の自宅でやっているんだ」とのこと。山の中には1000人以上の人たちがアタを編んで暮らしているそうです。そして、出来上がり次第、このアタの村にやってきて、お金をもらって帰るのだとか。
 「普通の大きさのバッグだと、編むのにどれ位かかるの?」と聞くと「ハンドバッグだったら一ヶ月から一ヶ月半くらいだね」と、平然と言います。「え、僕達が1万円位で買うこのバッグが一ヶ月半!」
「それだけじゃないよ。編んで一ヶ月半、乾燥させて燻して最終チェックして、ニヶ月はかかるんだよ」と重ねて言いました。一個のバッグに一ヶ月半もニヶ月もかかるなんて…さながら宝物の様なハンドメイド製品です。
僕達が9月の頭に注文したアタ籠は12月に完成するそうです。バリ島からコンテナに乗ってやって来ますので、ティラキタに到着し、お客様にお送りできるのは1月か2月ごろです。原産地の村から、直接やって来るアタの籠。くんくん嗅ぐと、もしかしたらココナッツの燻製の香りがするかもしれませんね。
ぜひ、お楽しみに!
「普通の大きさのバッグだと、編むのにどれ位かかるの?」と聞くと「ハンドバッグだったら一ヶ月から一ヶ月半くらいだね」と、平然と言います。「え、僕達が1万円位で買うこのバッグが一ヶ月半!」
「それだけじゃないよ。編んで一ヶ月半、乾燥させて燻して最終チェックして、ニヶ月はかかるんだよ」と重ねて言いました。一個のバッグに一ヶ月半もニヶ月もかかるなんて…さながら宝物の様なハンドメイド製品です。
僕達が9月の頭に注文したアタ籠は12月に完成するそうです。バリ島からコンテナに乗ってやって来ますので、ティラキタに到着し、お客様にお送りできるのは1月か2月ごろです。原産地の村から、直接やって来るアタの籠。くんくん嗅ぐと、もしかしたらココナッツの燻製の香りがするかもしれませんね。
ぜひ、お楽しみに!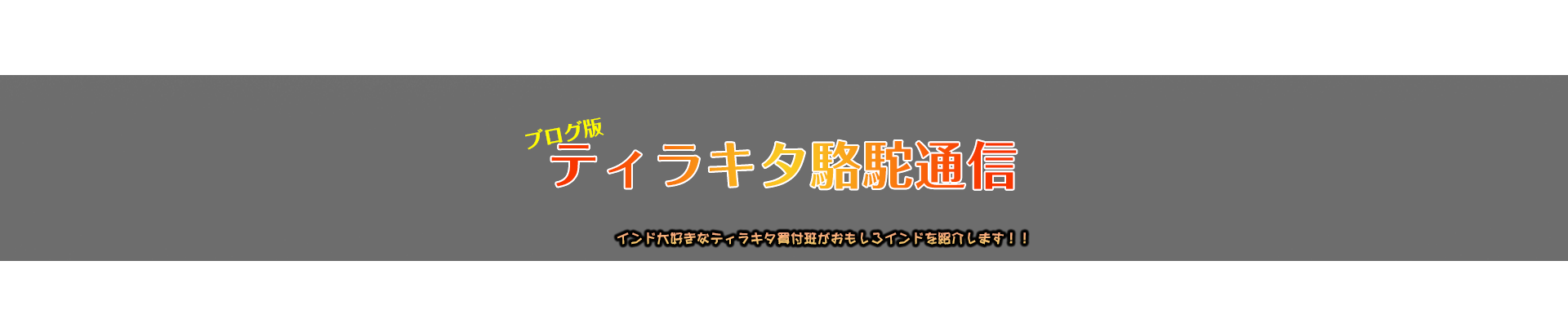

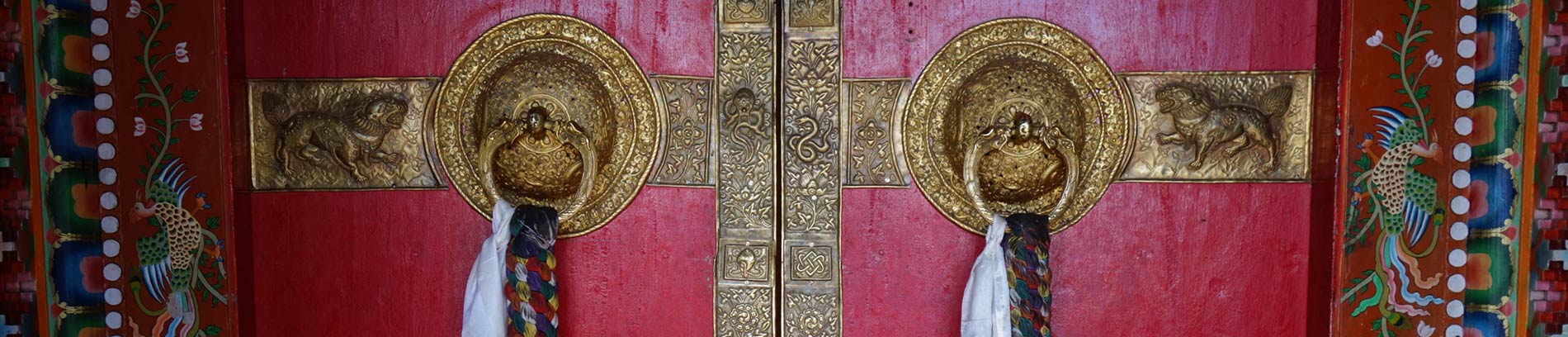

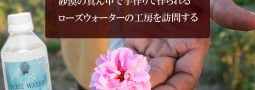
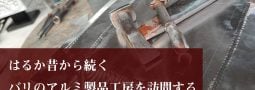




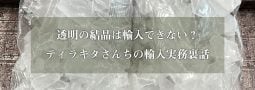
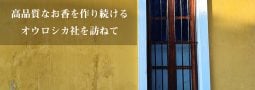
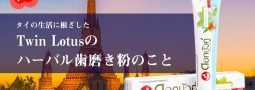








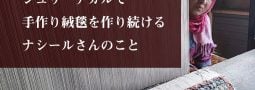
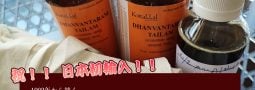
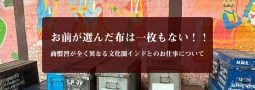
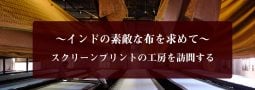
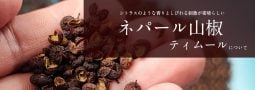





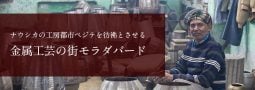
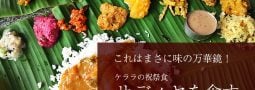
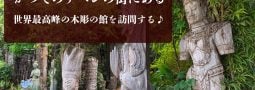



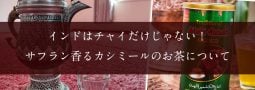




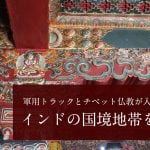
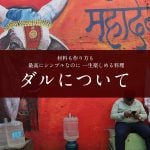


骸骨がいっぱい!インドネシアの風葬の村にはびっくりしました。文化の違いってことだと思うけど、世界は広いですね。