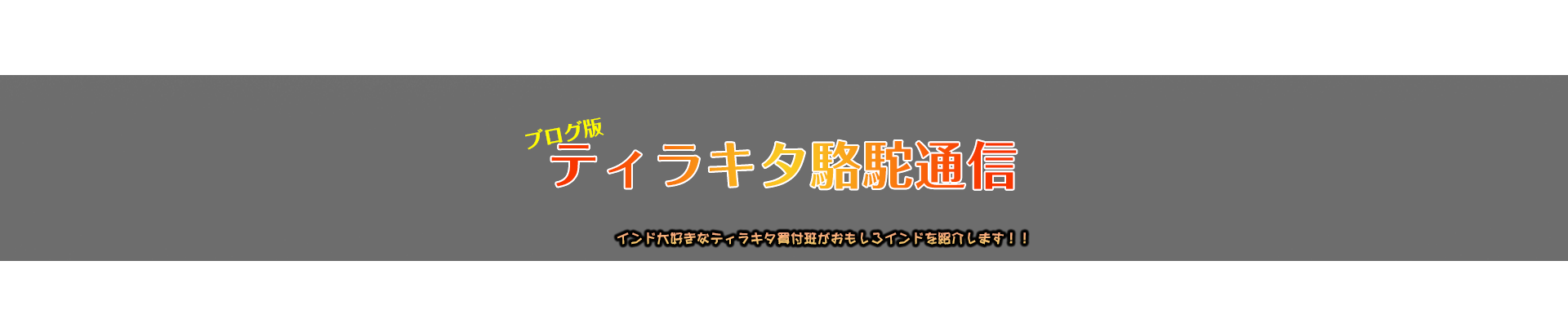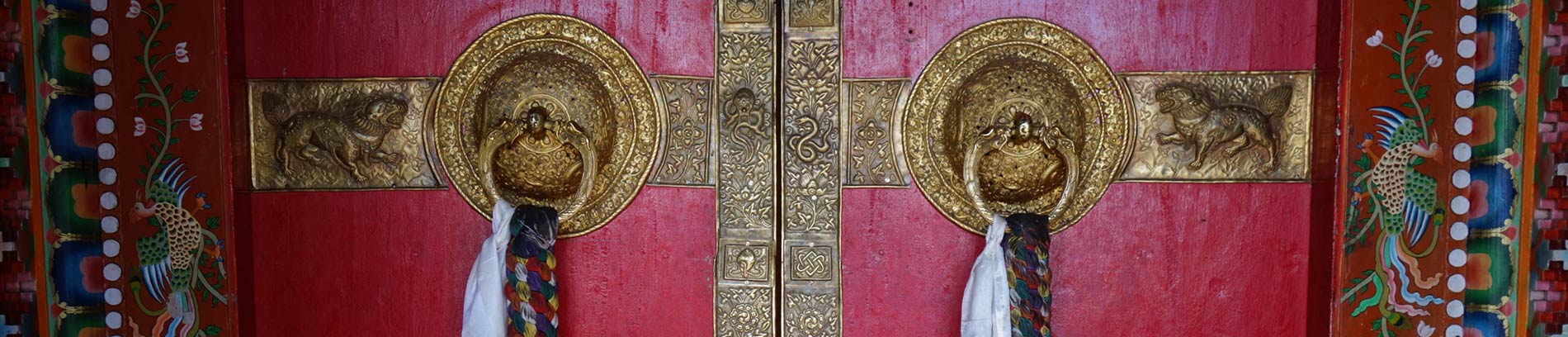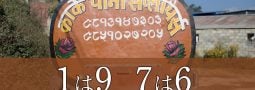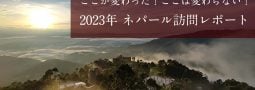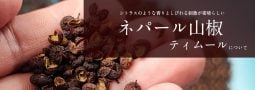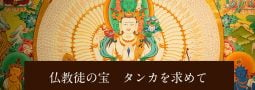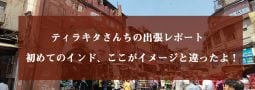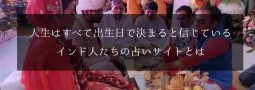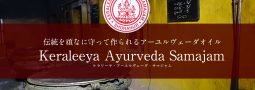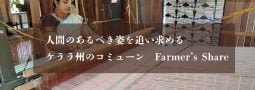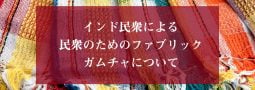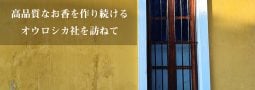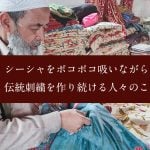やってみなけりゃわからない!ネパールで家造り
 ネパールの裏と表が見えてくる。
どっちが裏でどっちが表かわかんないけれど、だんだん、どっちも見えてくる。
どこか懐かしくって心地よいネパールに酔ってばかりも居られない、何だよ~またかよ~かんべんしてくれよ~みたいなネパールがどんどん積み重なっていく。これがネパール暮らしってことらしい。
ネパールに永く居るなら自分の家に住みたいと、家造りを始めたのがきっかけに、とんでもないスゴイことになってしまった。お金と時間と計画が、ぜ~んぶ流れていった。
建築現場にやって来る職人たちは、俺流に仕事をする人ばかり。出来上がったものが気に入らないと文句言ったってムダなコト。頭ん中ひっくり返りっぱなしでやってきたネパール家造りなのだ。
ネパールの裏と表が見えてくる。
どっちが裏でどっちが表かわかんないけれど、だんだん、どっちも見えてくる。
どこか懐かしくって心地よいネパールに酔ってばかりも居られない、何だよ~またかよ~かんべんしてくれよ~みたいなネパールがどんどん積み重なっていく。これがネパール暮らしってことらしい。
ネパールに永く居るなら自分の家に住みたいと、家造りを始めたのがきっかけに、とんでもないスゴイことになってしまった。お金と時間と計画が、ぜ~んぶ流れていった。
建築現場にやって来る職人たちは、俺流に仕事をする人ばかり。出来上がったものが気に入らないと文句言ったってムダなコト。頭ん中ひっくり返りっぱなしでやってきたネパール家造りなのだ。
目次
■番頭役は番頭役になれず。
ネパールで家を建築する場合、その敷地内に、簡易的な小屋を造って番頭役を雇って住んでもらうのが一般的だ。 レンガで積み上げた小屋に、トタン屋根で覆って、ドアと窓は、廃物利用で設置するだけ、中にはベッドを一台、薪やガスボンベ、調理用具一式と布団一式は、用意してあげればOKなのだ。 あとは何しろ、建築中の資材の流れや材料の管理、夜は警備役をしてくれるはハズ??だったのが上手くいかなかった。 ネパールでの家造りでは、すべての建材は自分たちで調達し、家にストックして置き、職人それぞれに配分して作業をしてもらうこととなる。 そのために前もって、建材、衛生器具、電材、配管材、ペンキ、あらゆる材料、すべてを用意しておくのだが、番頭役が管理なんてしてくれないし、おまけに買ってきた物が消えてしまったことなんてザラにあるのだ。 そんな番頭役は次々と選手交代を繰り返し、最後には、もうかんべんしてくれ~!番頭は居なくていい!となるまで、かなりの時間がかかった。 3人目の番頭は酒飲みだった。名前はノンベだ。
まだ40代だと言うのに初老の男にしか見えない風貌だ。
建築現場の夜は、泥棒避けには番頭が居て欲しい訳なのに、毎晩酒飲んで爆睡なもんだから、さあ困ったもんだ。ノンベの次の適任はすぐ見つからず、ノンベに番頭をしばらく任せるしかなかった。
しばらくして次の番頭が決まって選手交代となったが、それでホッとしたわけでもない。次の番頭もまた、いろいろとしでかしてくれるのであった。
あれから時は経って、ノンベが同じ村の中で、牛の放牧や畑仕事をしている姿をよく見かける。最近では小さな店を始めたらしく、これがなかなか上手くいっているらしい。
番頭役には向いていなかったが、ノンベは、ノンベらしく生きているようだ。
3人目の番頭は酒飲みだった。名前はノンベだ。
まだ40代だと言うのに初老の男にしか見えない風貌だ。
建築現場の夜は、泥棒避けには番頭が居て欲しい訳なのに、毎晩酒飲んで爆睡なもんだから、さあ困ったもんだ。ノンベの次の適任はすぐ見つからず、ノンベに番頭をしばらく任せるしかなかった。
しばらくして次の番頭が決まって選手交代となったが、それでホッとしたわけでもない。次の番頭もまた、いろいろとしでかしてくれるのであった。
あれから時は経って、ノンベが同じ村の中で、牛の放牧や畑仕事をしている姿をよく見かける。最近では小さな店を始めたらしく、これがなかなか上手くいっているらしい。
番頭役には向いていなかったが、ノンベは、ノンベらしく生きているようだ。

■息抜きしすぎのペンキ屋
建築の仕上げはペンキ屋の登場だ。リーダー格が1人と2人の職人のチームが請け負った。リーダー40代、あとの2人は30代。全員、所帯持ちである。 リーダーは奥さんを、職人の一人ウッザルは娘を亡くしている。 ペンキ屋の一日の日当は1,200ルピー約1,200円である。 ネパールの家は、セメント造りなので外壁から内装まで、ペンキで仕上げることとなる。外壁の塗装には、竹と縄で足場を作り、サーカスのごとく器用にペンキを塗る姿はカッコいい。 ペンキ屋の作業は朝9時から2時まで、一時間休憩、3時から6時までで作業終了である。 その間の一服はかかせない。タバコは1箱210ルピー。賃金の安い労働者でも、ヘビースモーカーは多い。13才くらいの子供でもタバコを吸いながら働いているのを見かける。タバコは仕方ない。
困ったことにペンキ屋は、ハッパを吸っているのだ。塗装作業の早い彼らの手が、いつもより遅くなったら要注意なのだ。家で吸ってくれと言っても効き目はない。これも仕方ないのかもしれない。そこんところは、ネパールはユルイ感じで流しておこう~となってしまうのだ。
もう1人の職人、クマールは愛嬌のあるお調子者だ。奥さんがしっかりしているので、本人はサボるのが超得意だ。インド音楽をガンガンに鳴らしながら作業をするので、時にはこっちも楽しい気分になる時もある。
その間の一服はかかせない。タバコは1箱210ルピー。賃金の安い労働者でも、ヘビースモーカーは多い。13才くらいの子供でもタバコを吸いながら働いているのを見かける。タバコは仕方ない。
困ったことにペンキ屋は、ハッパを吸っているのだ。塗装作業の早い彼らの手が、いつもより遅くなったら要注意なのだ。家で吸ってくれと言っても効き目はない。これも仕方ないのかもしれない。そこんところは、ネパールはユルイ感じで流しておこう~となってしまうのだ。
もう1人の職人、クマールは愛嬌のあるお調子者だ。奥さんがしっかりしているので、本人はサボるのが超得意だ。インド音楽をガンガンに鳴らしながら作業をするので、時にはこっちも楽しい気分になる時もある。
■出稼ぎへ行くネパール人
池袋のマックでネパール人に、いらっしゃいませ~と言われた時は、何だか嬉しかった。 最近ネパール人出稼ぎ組が、どんどん日本へ行っているらしい。 近所をぐるっと見渡しても、各家で1人以上は日本をはじめ、外国へ働きに出ているようだ。 建築現場に集まって来る職人たちの中でも、マレーシア、ドバイ、サウジアラビア、インドなどに出稼ぎ経験のある職人が、ぞくぞくといる。 彼らは一度出稼ぎに行ってそのルートをモノにした人は、何回も働きに出ているようだ。出稼ぎで稼いだ金でネパールに家を建てる、という人がほとんどである。 ネパールでは安定した、賃金の良い仕事は見つけにくい。 外国へ行って稼ぐんだ!!というハンパじゃない意気込みがある。 石屋のシャムは20代のころから、うちの建築現場に来ている石職人。
10代の頃に田舎からカトマンズに出稼ぎに来て、石屋に住み込みで働き、今では立派な石職人となっている。
彼の積み上げた石塀が、村の景色となっているのが、個人的に好きである。
彼は小さい頃から働いているので学歴は無い。腕があっても学歴がなくては外国出稼ぎはできない。大きなお世話だが、そういうのって、もったいないと、勝手に思っている。
彼もかなりの酒豪である。飲みすぎた次の日は仕事に来ない、気が向かない時も働かないというのが徹底しているから解りやすい。仕事をすれば人一倍、手早くできる職人であるが、安定して仕事をするという習慣が無さそうだ。
シャムは、ふたりの男の子の父親である。ふたり目が生まれる時、半分産まれそうな状態の母子を、夜中に病院まで搬送した。
いつ産まれるか?産む準備は大丈夫か?それさえ、行き合ったりばったりなのには驚いた。かなりワイルドな出産だったが、その時産まれた次男坊は、やんちゃに育っていてたくましい。
石屋のシャムは20代のころから、うちの建築現場に来ている石職人。
10代の頃に田舎からカトマンズに出稼ぎに来て、石屋に住み込みで働き、今では立派な石職人となっている。
彼の積み上げた石塀が、村の景色となっているのが、個人的に好きである。
彼は小さい頃から働いているので学歴は無い。腕があっても学歴がなくては外国出稼ぎはできない。大きなお世話だが、そういうのって、もったいないと、勝手に思っている。
彼もかなりの酒豪である。飲みすぎた次の日は仕事に来ない、気が向かない時も働かないというのが徹底しているから解りやすい。仕事をすれば人一倍、手早くできる職人であるが、安定して仕事をするという習慣が無さそうだ。
シャムは、ふたりの男の子の父親である。ふたり目が生まれる時、半分産まれそうな状態の母子を、夜中に病院まで搬送した。
いつ産まれるか?産む準備は大丈夫か?それさえ、行き合ったりばったりなのには驚いた。かなりワイルドな出産だったが、その時産まれた次男坊は、やんちゃに育っていてたくましい。

■女性が建築現場で働くということ
ネパールでも、女性が外で働くようになって来ているとは言っても、経済的に貧しく学歴も無い女性にとっては、働く窓口は狭い。 彼女らが、労働場所として選ぶ中に建築現場の仕事がある。 女性だからといって軽作業であるわけではない。 背負いカゴに、レンガや砂、石などを運ぶ重労働だ。 彼女たちの首と手足を見ると、ビックリするほど硬く太くガッチリとしている。 うちの現場にもたくさんの女性たちが出入りした。 彼女たちは、手に職を持った職人ではなく皆、そういった重労働者たちである。子連れの女性もいた。連れてこられた子供は、まだ学校に入る前の年頃3、4歳くらいの子たち。 一日中、建築現場のホコリだらけの中、親の働く横で砂遊びをしていているだけである。そのまま学校へは行かず、建築現場で働き始める少年たちも多い。 ラクシュミという女性が、うちの現場で長く働いてもらった。バウン族の彼女は、賢く働く女性である。彼の旦那も時々、働きに来たが、彼らの家では、奥さんが外で働き、子供ふたりの面倒と食事は旦那の担当らしい。 旦那の兄弟は皆、お坊さんで、彼だけはお坊さんにならないで主夫をしていた。(バウン族はお坊さんの家系が多い) ここ最近、うちの現場から離れてから、彼ら家族は、村の寺を守る番頭役を引き受け、お寺の仕事をしているらしい。結局、バウンらしい職に勤めるところに、とりあえず修まったようだ。
先日、小高い丘の上にある村の寺に散歩に行った時、ラクシュミは、お寺の掃除や片付けに忙しそうだった。旦那は家の中で寝ていた。
ここ最近、うちの現場から離れてから、彼ら家族は、村の寺を守る番頭役を引き受け、お寺の仕事をしているらしい。結局、バウンらしい職に勤めるところに、とりあえず修まったようだ。
先日、小高い丘の上にある村の寺に散歩に行った時、ラクシュミは、お寺の掃除や片付けに忙しそうだった。旦那は家の中で寝ていた。

■おしゃれなタイル職人のインド人
ネパールにはインドから出稼ぎに来ているインド人も少なくない。 うちの現場にも、たくさんのインド人がやってきては、いろいろとエピソードを作って行った。 彼らが来た日は、現場がにぎやかと言うよりうるさい。
黙って仕事をする民族ではなさそうだ。
ヒンズー語が一日中聞こえる中、そのわりに作業が遅いでもなく、早いでもなく、おしゃべりと作業効率は関係なさそうだ。
タイル貼り職人は、ベンガル人、コルカッタの人だ。
職人なのに、いつも革靴を履いているのが気になった。
彼はいつもおしゃれをしてやってきた。
汚れる作業に綺麗な服装で働くという彼流のスタイルだった。
彼らが来た日は、現場がにぎやかと言うよりうるさい。
黙って仕事をする民族ではなさそうだ。
ヒンズー語が一日中聞こえる中、そのわりに作業が遅いでもなく、早いでもなく、おしゃべりと作業効率は関係なさそうだ。
タイル貼り職人は、ベンガル人、コルカッタの人だ。
職人なのに、いつも革靴を履いているのが気になった。
彼はいつもおしゃれをしてやってきた。
汚れる作業に綺麗な服装で働くという彼流のスタイルだった。
■インドカレー賄い食は、ネパール職人に人気が無い
毎日自宅でロティを作ってカレーを1人分だけ作る彼は、インドからの単身赴任者。 彼の本業は、夜の新聞印刷工場で働く会社員だ。 昼間だけ、うちの現場で働いていた。 うちにやってきたインド人1号さんだけど、建築のことは全くわからないので、かんたんな建材の調達や雑用係りと、職人たちの賄い食を作ってもらったりしたが、ここに来るネパール人はインドカレーを好まなかった。 同じカレーと言わないでくれ!というのもわかる気もする。日本にインドネパールカレーの店という、良くわからん名前の店があるが、やっぱり別物だということがわかる。 職人受けはしなかったが、休日に家に呼んで料理をしてもらったりした。彼のカレー作りは独特の料理法がある。時々作ってもらってマネしてみたが、やっぱりインド人が作るカレーは本場もんだった。

■土壁も造ってみた
ネパールのタライ地方に行くと土壁の素朴な家がある。 タル族のアーティストチックな建物は彼らの独特の文化である。自分の家にも、そんなタルの家のようなイメージをどこかに取り入れたいと思ったので土壁を造ることにした。 作業するのはタル族の20代のお兄ちゃんたちだ。住み込みで働いてもらった。タル族の彼らは、田舎の子たちというよりもっと原始的な子たちだった。時々話が噛み合わないのは、そういうギャップなのかとも感じた。 土壁作りは、土、砂、牛糞、鉱物など、規定の配分で交ぜ、壁となる部分に型枠を作って、その中にすこしづつ、交ぜた材料の土を入れて、上から、平たい板状の道具で突っつく、それを何回も繰り返し行うと、地層のような感じの土壁が出来上がる。時間と労力のかかる作業となる。 最近のネパール人住宅は、セメントでできた壁が一般的で、造るのも簡単である。これが冬は頭が痛くなるほど寒く、夏は暑くてたまらない。 これが土壁になれば、冬は暖かく夏は涼しいので、この快適さを手に入れるために、土壁を造った。何を今さら面倒くさいことを、 と周りに散々言われ続けた。結局、今となっては、土壁の良さは格別である。見た目も美しい。

■家具類は買わずに造る
家具が欲しければ木大工に注文して造ってもらう方が、部屋の寸法にあったオリジナルなものが手に入る。内装家具は、マガル族の大工に造ってもらった。 隙間家具やキッチン周りの棚、電気カバー、下駄箱など。部屋の天井も木材を使って仕上げた。これが昭和風に仕上がって気に入っている。 この大工、珍しく根気強く付き合ってくれた職人でもある。ネパールの職人に注文する場合、ネパール風のものを造ってもらうことには問題はない。 オリジナル製を求めると、かなりの時間と労力がかかるのだ。これは家全体に共通することで、オリジナルを求めると、かなりの災難続きの結果、やっと思い通りのものが手に入るかどうか?ということとなる。 自分の家が出来て行くというのは楽しいものだ。でも、こんなに永くやってらんね~。というのも本音である。嘆くのも飽きたので、諦めるコトとやり直す持続力は、持ち続けたいという理想はある。
自分の家が出来て行くというのは楽しいものだ。でも、こんなに永くやってらんね~。というのも本音である。嘆くのも飽きたので、諦めるコトとやり直す持続力は、持ち続けたいという理想はある。
 家までの路地入り口に電信柱が立っていて、電線がこんがらがっている。ネパールでは良くある光景だ。こんなのでも電気は、ほぼ各家庭に配られているが、トラブルも多い。
とにかく、ほぼ電気は来ているのだから、これでいいのだ!という雑な感じがネパール風のようだ。家造りも、ほぼ家であればいいのだ!ということも、今となっては、充分ガッテン出来ている。
家造りを始めてから、その間にネパール地震もあった、ガスや電気や水も、好きなように使えなかった。それに加えて、とにかく職人たちがスゴイやつらばかりなんだ!
やってみなけりゃわからない。
ネパールでの家造りで、ずいぶん鍛えられたことと、新たに雑な志向回路が備わったことは、大きな収穫であると言える。
家までの路地入り口に電信柱が立っていて、電線がこんがらがっている。ネパールでは良くある光景だ。こんなのでも電気は、ほぼ各家庭に配られているが、トラブルも多い。
とにかく、ほぼ電気は来ているのだから、これでいいのだ!という雑な感じがネパール風のようだ。家造りも、ほぼ家であればいいのだ!ということも、今となっては、充分ガッテン出来ている。
家造りを始めてから、その間にネパール地震もあった、ガスや電気や水も、好きなように使えなかった。それに加えて、とにかく職人たちがスゴイやつらばかりなんだ!
やってみなけりゃわからない。
ネパールでの家造りで、ずいぶん鍛えられたことと、新たに雑な志向回路が備わったことは、大きな収穫であると言える。